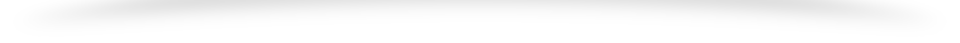1970年頃から東京空襲に関する資料を丹念に集め、記録してきた作家の早乙女勝元さん(「東京大空襲・戦災資料センター」館長)。悲惨な戦争の記憶を後世に伝えようと奮闘を続けてきた、早乙女さんの半世紀にわたる歩みを伺いました。
【コンテンツ】
- 戦時中の生活:少年時代のハンディがその後の原動力となった
- 戦災補償へ向けた取り組み:不条理を今後の世代に残してはならない
- 空襲を後世に伝える施設:行政がやってくれないなら、自分たちの手で
スポンサーリンク
1.戦時中の生活:少年時代のハンディがその後の原動力となった
ほとんどの男の子は軍人志望
―はじめに、戦時中、社会はどのような雰囲気だったのでしょうか。
私は昭和7(1932)年の3月生まれです。前年昭和6(1931)年9月に満州事変が起き、日中戦争の口火が切られました。したがって昭和20(1945)年の8月15日まで、15年戦争と言われますが、平和を見ることも聞くことも、触ることもなく、続けざまの戦争、戦争でした。アジアの大地から太平洋まで。そういう状況の中で、メディアと言っても大本営発表しかなかった。今にして思えば、信憑性はなかったです。新聞、ラジオ、学校教育、隣組、全部同じ情報です。
一言でいうと、日本が始めた戦いは聖戦。戦う日本軍は皇軍。天皇の軍隊ですね。日本軍が行くところ勝った勝ったで、日本が勝利するだろうということを、耳にタコができるほど教えられていました。したがって、ほとんどの男の子はね、軍人志望で少年航空兵に憧れていましたね。14歳で受けられるから。それから「七つボタンは桜に錨」の予科練(よかれん)※1と言いますよね。あれは15歳から。憧れの的でした。
※1 海軍飛行予科練習生
戦争も軍隊も怖かった
― 早乙女さんは、戦争と、それに邁進する社会をどのようにとらえていましたか。
僕は一般の傾向とちょっと違う面がありました。小説家を志す人間だから、文化的に恵まれていたと思われるかもしれないけど、あまりの貧困家庭で、しかも中卒ですからね。と言ってもそのときは国民学校高等科卒で、これが今の中学校に相当します。卒業は昭和21年。
貧困家庭でどうなのかということですけど、予科練を目指す友達なんかは、経済的にも成績的にも恵まれていたと思いますよ。だから率先して軍国主義の先陣を切ったと思います。女の子だって日赤※2を通じて従軍看護婦になりたいと思うのはやはり優秀な子なんですね。優秀な人材ほど…特攻隊がそうだと思います。自爆死させたというのは惜しいことをしたと思いますね。そんな軍隊どこにもありませんから。世界中見ても。特攻作戦というのは自爆死のことですから。
※2 日本赤十字社
対して私は、なんていうか、底辺の子どもなんです。さらに言えば、虚弱体質なんです。簡単に言ってしまえば、戦争の役に立たない。だから戦争がとっても怖かったですね。軍隊も。今でもそれは変わりありません。本能的に、戦争はいやだなあ、軍人になりたくないなあ、と思っている男の子はそうはいなかった。ある意味では、少年期のたいへんなハンディですね。そのハンディが、その後の私自身の人間形成につながっていきます。
スポンサーリンク
自分よりも下の人がいるということの驚き
ー 当時はどのように過ごされていたのでしょうか?
昭和19年秋からは学校が終わっちゃって、行かなかったですよ。勤労動員が始まり、隅田川沿岸の大鉄工所で働きました。そこには朝鮮半島から連れてこられた青年たちがかなりいて、溶鉱炉の仕事についていた。そこで見たこと感じたことは、学校では得られるものではないと思います。私なんかは、自分が最低の人間だと思っていたけど、もっと下の人がいるんだということが分かりました。日本人労務者の態度はすごく横柄でしたよ。監督を兼ねるわけですからね。でも当時のコリアンは、同胞じゃありませんか。植民地支配下のね。地図を見れば、同じ赤色で塗ってあるのに、それなのに、なぜそんな扱いをするんだと思いましたね。
さっき言ったけれど、貧困で虚弱体質だったから、遊び友達もあまりいなくて、孤立していました。そうすると一人きりになっちゃう。一人きりでできることは、読んだり描いたりです。絵描きになろうと思った時期もありました。子どもの時からそうやって余分なことを体験したから、書きたいことがたくさん出てきたんです。それで物書きになろうと。
<早乙女さんの東京大空襲ルポルタージュ>
東京大空襲のあの日、焼夷弾の火の海の中で人びとはどのようにもがき、生死をさまよったのか。あの日を生き延びた人々への詳細なインタビューを元にした、悲劇のルポルタージュです。1971年刊。
次は ➡ 2.戦後の戦災補償へ向けた闘い
★関連記事
スポンサーリンク